キムケゴール
- ナムル皇帝

- 2023年7月30日
- 読了時間: 2分
1866~1930
自身の人生を見つめ直しすぎた人物。
彼は特段裕福でも貧困でもない一般的な家庭に生まれたが、
感受性が豊かで、幼少期の頃から
・親が手放した自転車の気持ちを思って号泣
・友達によって惨殺されたトンボの気持ちになって号泣
・あんまり洗わず酷使されていたブリーフの気持ちになって号泣
・なんかよくわかんないけど居酒屋で口論してビンタされていた成人男性の気持ちになって号泣したりしていたという。
泣く、という負の感情にばかり感受性が豊かであったせいか、
徐々に負の感情の頂点、「死」に対する思想へ傾倒するようになる。
「死に至る病」とは何かを著した「アレカコレカクレカ」(1899)
に彼の思いは記載されており、結局のところ、とどのつまり一切合切
人生とは人それじて「悲しみ」の閾値が個体差で割り振られており、
「悲しみ」の一定の蓄積が「死」に至るという
ギャルゲーの信頼度のような理論を掲載した。
当時は1世紀前のキタマクラがあったこともあり、「死」は悲劇的であるということから
全世界で「死」に対することを記載した彼の書物は発禁となっていたが、
21世紀に入り原本が見つかり、エロゲマン(1982~現在)によって翻訳されている。
コラム①「死」よりも「痔」が大変だったキムケゴール
彼は心の中は常に「死」に纏わる思考で埋まっていたが、
体外的には常に「痔」に悩まされていたという。
幼少期に便秘気味だった経験を持つ両親からヤクルトを異常投与され、
便がスムーズになった分、菊門の酷使が状態化し、痔になったと言われている。
その痛みも彼が「死」を考える、現世から逃避したくなる要因であったかもしれない。
最期はヤクルトをサボり腸閉塞にて死去した。
コラム②応用されている彼の思想
彼の「悲しみの個体差毎の閾値への到達=死」については様々な業界で応用されている。
例えば
・「2次元女性キャラへの好感度閾値到達=付き合う、逢瀬する」は
今日のギャルゲーに基本搭載。
・個体差があることでゲームの深さを追求した「バケモン」
などが応用の一種とされている。全てはエロゲマンのお陰なのである。
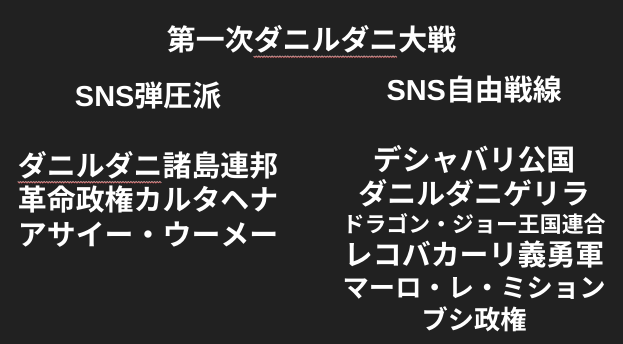
コメント